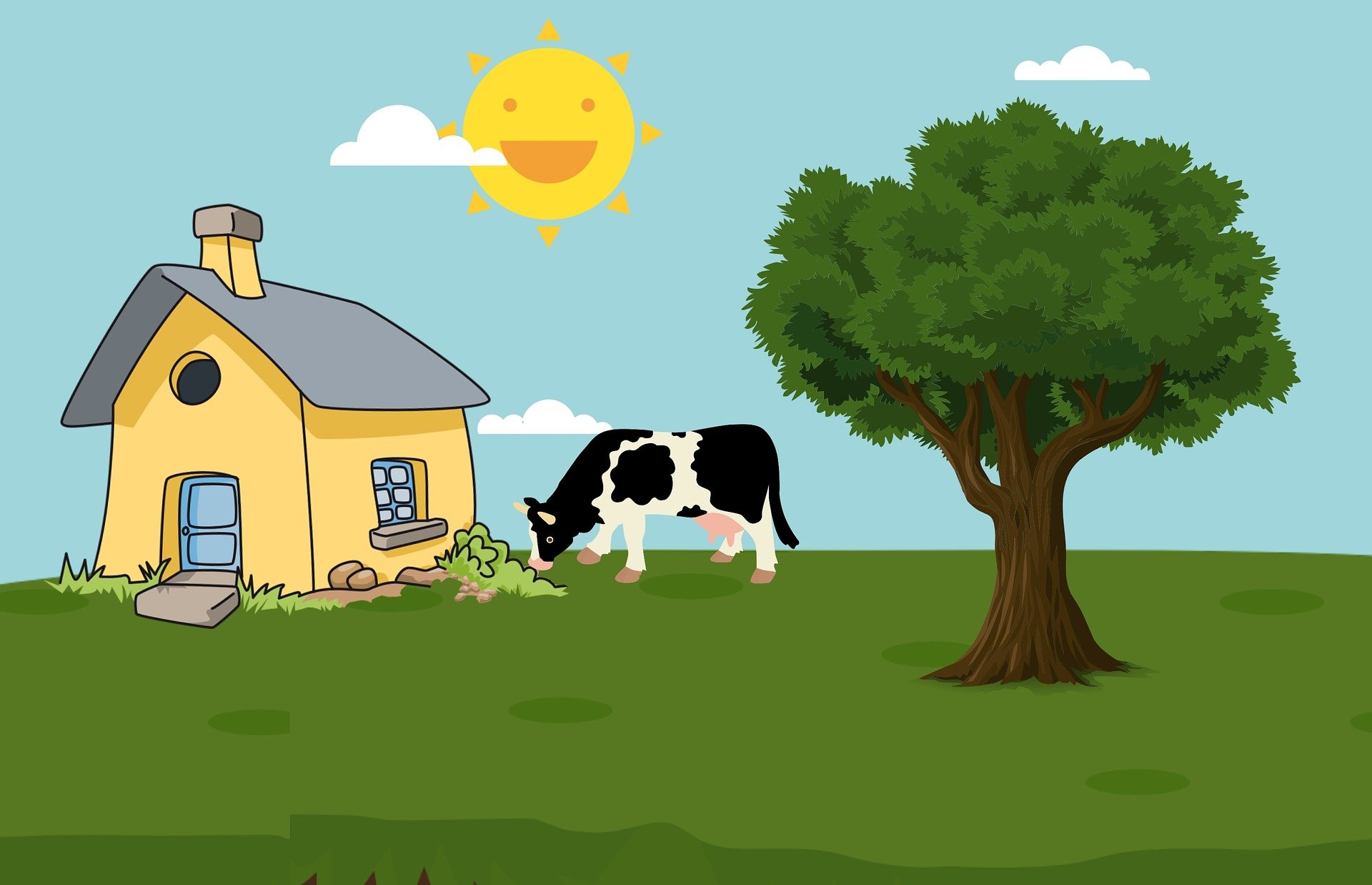❬児童虐待を防ぐ一つの方法❫
児童虐待の始まり
- 今、私は知らず知らずに我が子に虐待もしくはそれに近いことをしなくてはならないという気持ちになっている
- 今、私は知らず知らずに我が子を虐待もしくはそれに近いことをしようとしている
- 今、私は知らず知らずに、我が子を虐待もしくはそれに近いことをしている
- 今、私は児童虐待の容疑で警察に捕まり、連日マスメディアに一斉に取りあげられている
このように最初は「知らず知らずに」なのだと思います。
最初から虐待しようとやっていることではなく、意識せずに知らず知らずにやってることが多いと思われます。
全部が全部ではないですが
赤ちゃんなどの幼児や児童を持つ親はこのような気持を持った末に児童虐待を起こしているのだと思います。
児童の定義
児童福祉法第4条において、児童を「満18歳に満たない者」と定義し、
「1歳未満」が乳児、「1歳から小学校就学の始期に達するまで」が幼児、「小学校就学の始期から18歳に達するまで」とされております。
ここで記載する「児童虐待」の児童とは乳児、幼児の話になります。
児童虐待の種類
児童虐待には下記の4種類があるといわれております。
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- ネグレクト
- 性的虐待
児童虐待を未然に防ぐには
しかし、児童虐待を防ぐ方法があります。
すべて児童虐待が無くなるということではありませんが。
しかし、ある方法で赤ちゃん用具を変えることで虐待を防ぐ可能性があります。
ある意味、
荒唐無稽、奇想天外な話と思われるかもしれません。
その用具とは
赤ちゃん靴(ベビーシューズ)
のことです。
詳しくはこの後に記載します。
靴を替えてあげることで、「児童虐待」を避けることができるのです。
児童虐待防止と赤ちゃん靴(ベビーシューズ)との関係
「まさか、私が、自分の子供に虐待しようとしている?もしくはそれに近いことをしている?」
つまり児童虐待を・・・
と感じている人は、騙されたと思い、
このサイトを最後までみてください。
関係者のみなさんは永年に渡り、公的にも私的にも、児童虐待を防ぐために努力されていると思います。
その取り組みには、頭がさがる思いです。
主な活動
- 児童虐待防止法制定
- こども家庭庁の設置
- 児童相談所虐待防止ダイヤル
- 「いちはやく」189
- オレンジリボン運動
など
このように
児童虐待対策を講じていますが、残念ながら、年々増加傾向が続いております。
その対策は今後も時代の流れに応じて見直し、更新されていくことと思います。
児童虐待全体の一部でもいい、被害を受ける児童が少しでも少なくなれば、また、加害者となる可能性のある親たちを未然に防ぐことができればという思いで書いています。
本題に入ります。
ある種類の赤ちゃん靴(ベビーシューズ)を替えるべき理由
ここから話が大きく逸れ、滑稽無形な、奇想天外な話になるかもしれませんが
赤ちゃん靴(ベビーシューズ)に児童虐待を誘発するものがあったとしたら、そのような赤ちゃん靴(ベビーシューズ)を履かせなければいいのです。
もちろん学術的に認められたものでなく仮説になります。
どんな赤ちゃん靴(ベビーシューズ)を避けるべきか
靴の形には足を入れるトップが
- 標準的なもの
- 標準より大きめのもの
いわゆる「オーバーシューズ」
と呼ばれるものがあります。
このようなオーバーシューズ気味の赤ちゃん靴を避けた方がいいということです。
どうしてオーバーシューズ気味の赤ちゃん靴を避けた方がいいのか?
これは学術的に裏付けされたものではありません。
そんなもの話にならないと感じるかもしれません。もし、そう思われた方はこのサイトから退去してもらっても結構です。
私がこの主張は長年の経験で感じたことに由来してます。それだけのことかと思われても仕方ありませんが。
避けるべき理由
私なりに理由を考えてみました。
人間は生まれつき人と人の親しい関係で生きていくものだと考えます。
それは
- 大人対大人
- 大人対子供
- 大人対赤ちゃん
- 子供対赤ちゃん
相手が違っても みんな一緒です。
人間に生まれた以上、意義のある楽しい人生を送りたいと思ってるはずです。
意義のある楽しい人生を送るには
本人も相手の人もお互いに
「親しみ」を持って接することが基本です。
ある人が親しみを持って接してきたのに、親しみで返してくれなかったら、どうなりますか?
1、2回くらいなら、そんなこともあるかなと我慢するかもしれません。
しかし、それが1週間、1ヶ月と続いたらどうなるでしょうか。
「親しみ」をもって接しても、相手からそれが返ってこなければ、自分の関心も次第に薄れていきます。
これは
大人対赤ちゃんにもあてはまると思います。
ここに
知らず知らずに
「まさか、私自分の赤ちゃんに虐待らしきことをしているのかしら」と感じることになるのではないでしょうか。
児童虐待のニュースが流れるたびに防ぐことができなかったのかなと思います。
世の中、日進月歩で変化しています。
他の要因も確実にあると思います。
が、
信じる信じないは別にして、少しでも可能性があれば、ダメもとでも試してみる価値があると思います。
「児童虐待を起こしてしまった」
と
「未然に防ぐことができた」
では
天と地の違いがあります。
赤ちゃんは意思表示ができない
赤ちゃんには
かわいい服を着させてもらっても
かわいい赤ちゃん靴(ベビーシューズ)を
はかせてもらっても
赤ちゃん本人はこの服、靴が
「いいよ好きよ」なんて言えません。よちよち歩きで言葉もまだ話せない赤ちゃんには意思表示ができないのです。
だから、赤ちゃんのために用意するものについての親の選択が非常に大事になります。当たり前ですが、親は重責を担っているのです。
判断を誤れば重大なことになる可能性があるのです。
確かに赤ちゃん靴(ベビーシューズ)なんて長い人生の中では小さなことかもしれません。
しかし、マスメディアで報じられている事件になってしまってからでは、遅すぎます。取り返しのつかないことになってしまいます。
大人は赤ちゃん(子供)とも「親しみ」の関係で接しなければならないのです。
では児童虐待を減らすには
序文で書いた気持ちを感じられる親は
すぐに行動を起こしてください。
行動とは、該当する(トップがオーバー気味のやつ)赤ちゃん靴(ベビーシューズ)を捨てることです。
靴箱の奥に仕舞うのではなく、捨てることです。
赤ちゃん靴(ベビーシューズ)には孫のためにと親、親戚からプレゼントされたものもあるでしょう。
ここは勇気をもって捨てることです。
今も公私にわたり児童虐待防止対策が行われております。
私のある意味滑稽無形な、奇想天外な提案と思われるかもしれません。
でも、毎年増加している痛ましい児童虐待を減らす1つの手法としてやってみるのもありだと思います。